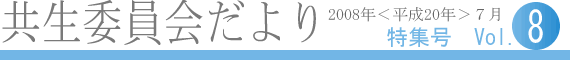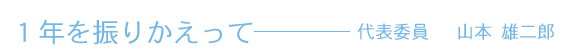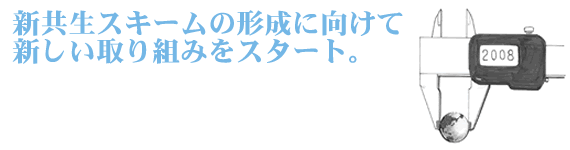共生委員会は2007年度(平成19年度)、第7期に入り、その活動についても、新しい取り組みを始めました。それは第7期のスタートに際し「新しい共生スキームができるまでの過渡期」と位置づけられ、「何らかのシステムチェンジを模索せざるをえない時期」に当たるとされたからです。 共生委員会がこうした取り組みをするようになったのは、空港会社の完全民営化が迫ってきたことに加え、成田空港問題をとりまく状況が大きく変わってきたことがきっかけでした。成田空港そのものも、北伸による平行滑走路の2500m化、ターミナルビルの増改築、アクセスの拡充など整備は順調に進み、完全民営化への準備も加速されています。 その一方で、航空や空港に関して、政府部内をはじめ、経済界や学界で、アジア・ゲートウェイ構想、オープン・スカイなどの議論が高まり、羽田再国際化を求める動きが強まってきました。また新しい空港法制を策定する準備が進んだのも、この時期の特徴といえるでしょう。 さらに空港周辺地域でも、注目すべき変化がみられるようになりました。共存共生から共栄へ、という動きがそれです。芝山町・成田空港共栄推進委員会に次いで、9市町で構成する成田国際空港都市づくり推進会議発足の準備が進みました。 このような、状況の大きな変化に、共生委員会としても、機動的に対応していかなくてはなりません。そのために、共生委員会の活動方式を改め、運営チーム、共生ワーキンググループ、共生スタディグループを発足させました。 運営チームで共生委員会活動の方向性を決め、それに基づいて共生ワーキンググループは円卓会議合意事項の点検など設置要綱に規定された本来の業務を遂行し、共生スタディグループは新しい共生スキーム形成の準備に向けた業務を担当することにしたのです。共生委員会活動の新機軸を打ち出したといっていいでしょう。 この1年間、この線に沿って活動を続け、12月には『共生委員会第7期中間総括』をとりまとめましたが、その評価としては「必ずしも軌道に乗ったとは言えないのではないか」ということになりました。状況の変化があまりにも激しく、その対応に追われたことなどが原因でしたが、新機軸を定着させる努力が必要であることに、あらためて思いを至しています。 共生委員会の第7期も、あと1年になりました。この先、国土交通省、千葉県、空港会社によって、新しい共生スキームを検討するプロジェクトチームが設けられることになっています。この検討にあたっては、共生委員会はもとより、共生財団ような関係機関、歴史伝承プロジェクトのような関連事業も含め、共生の全体像が論議されるでしょうが、たとえどのような方向が打ち出されるにせよ、「地域と空港との共生という理念は、成田空港がこの地にある限り続く永遠の課題」( 共生大綱)とされている以上、共生委員会としては、新しい共生スキームの構築に向けて着実に歩んでいかなくてはなりません。これからも、そうした見地から共生委員会活動を行っていきますので、いっそうの理解と協力をお願いいたします。 |