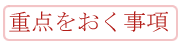
1.平行滑走路については話し合いにより解決/ 発着回数の増加については地元と協議[滑走路計画]
国・空港会社は、平行滑走路北伸案について、2005年(平成17年)7月から2006年(平成18年)3月末までに106回の地域説明会を行ってきたと報告しました。
今回の説明会は、自治体だけでなく直接、地元住民、とくに平行滑走路北側の集落に出向き、きめ細かく行ったということです。主な内訳をみると、成田市で32回、下総町16回、大栄町9回、芝山町9回、共生委員会7回などとなっています。
第1段階として、平行滑走路整備の北伸案にいたる経緯について、国が中心となり、7月20日から9月末までに32回の説明会を行いました。
8月4日、国土交通大臣は空港会社に、平行滑走路は北伸案により整備すること、北伸案および騒音対策は地元の理解と協力を得られるようきちんと説明すること、東峰区との話し合いの窓口は開いておくこと、を指示し、それ以降は指示内容も合わせて説明しました。
第2段階は、空港会社が主体となり、10月3日から12月20日まで、北伸案の具体的な計画、騒音予測コンター、環境とりまとめについて、41回の説明会を行いました。 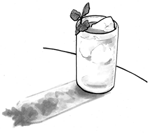
第3段階として、国・千葉県・空港会社は、1月19日から3月23日まで、騒防法区域指定の考え方、発着回数の22万回への増加、騒特法基本方針の見直しについて、33回の説明会を行いました。
また国、千葉県、空港周辺市町村、空港会社の四者は、国土交通大臣の指示以降、これまで重ねてきた協議経過について、つぎのように中間的とりまとめを行い、報告しました。
平行滑走路の北伸整備に係る確認書
(前文省略)
記
1.騒音区域の変更について
(1)騒防法について
四者は、国の第一種区域案について了承する。
(2)騒特法について
国、千葉県及び空港会社は、現在までに関係町から千葉県に提出された「航空機騒音障害防止地区とすべき地域」及び同「防止特別地区とすべき地域」の案について了承する。
ただし、地元協議が継続されている地域については、国、千葉県及び空港会社と調整しつつ速やかに案を作成することとする。
2.地元意見への対応について
四者は、関係市町村から提出された意見を真摯に受けとめ、誠実に対応する。
3.発着回数の22万回への増加について
千葉県及び空港周辺市町村は、空港機能強化の必要性を理解し、発着回数の増加について、地元意見を尊重の上、早期に結論を得るものとする。
4.その他(今後の協議について)
本書の内容のうち、今後確認を要する事項については、改めて四者で協議する。 |
| 平成18年3月23日 |
これらの報告を受けて共生委員は、「北伸案の説明を精力的に行ってきたことは評価するが、地元の理解を得ることが重要だ」と述べました。空港会社は、「市町の集約には当然、住民の方からの要望が整理されていると認識している」と答えました。
また委員から「発着回数が22万回に増えると、非常にうるさくなるのではという懸念が住民にはある」「4000m滑走路の方が重い飛行機が飛んでうるさくなるのでは」などの意見が出されました。
これについて空港会社は、「平行滑走路ができて飛んだ時に、騒音コンターからはみ出ることがあれば、当然、対策区域を見直すことになる」と答えました。
2.W値の逆転現象への対応[航空機騒音]
2002年(平成14年)4月に暫定平行滑走路が供用されてから、航空機の発着回数が増えたにも関わらず航空機騒音の評価値WECPNL値が減少するという事態が確認されました。さらに、現在の評価方式が地域住民の実感にそぐわないという指摘がありました。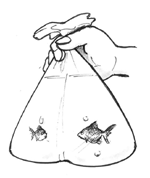
環境省は、これを受けて2004年度(平成16年度)、航空機騒音の評価方式についての検討委員会を設け、W値に関する調査・検討を続けてきました。国土交通省は、この委員会に学識経験者とともに参加しており、この度、2年目の調査・検討結果を以下のように報告しました。
・成田空港周辺の20の常時監視局において週別の数字で最大0.1から0.8デシベルの逆転現象が確認された。
・大阪国際空港、福岡空港、富山空港、広島空港で航空機騒音の曝露状況の実態把握を行った。
・2004年度(平成16年度)の検討委員会で示したW値の計算の修正案と、さらにもう1つのエネルギーベースによる評価方式Ldenで計算しても、数値上の逆転現象は発生しないことが確認された。
○ 環境基準式WECPNLと時間帯補正等価騒音レベル(Lden)の違い
WECPNLでは、航空機騒音のピークレベルのパワー平均値に時間帯別に重み付けをした飛行回数を補正しています。Ldenでは、時間帯別重み付け補正をした航空機騒音発生時のエネルギー総曝露量を1日の総時間で平均し算出しています。このためLdenでは、機数が増えれば評価量が上がるため、住民が受ける騒音感覚量により近い評価ができるのではと考えられています。検討委員会では、引き続き2つの騒音の評価方式について専門的な検討を続けるとしています。
これらの報告に対して、共生委員は「日本のWECPNLの評価方式に不備があったことはわかった。しかし不備が改善されたら正しく計算されたという証拠にはならない」「現在のW値は地元住民の実感している騒音値と乖離しているという声がある」「飛行機が倍になったら音も倍になるのでは、という住民の感じ方に国はどのような説明で納得させてくれるのか」などと質しました。
これに対して国は、「成田市や千葉県からも検討委員会に要望書が出された。逆転はいくつかの方式で解消されることがわかった。今後は、地域住民の実感にそぐわないという指摘にどのような形で答えていくのか、環境省も問題意識をもっているので、今後の考えを聞き、こちらの問題意識も伝え、みなさんに報告したい」と述べました。
3.22時台の便数(10便/日)の遵守[滑走路計画]
円卓会議の合意事項により22時台の発着回数は1日10便までとなっています。ところが発着回数は年々増え、2005年度(平成17年度)には、1日平均14.1便となりました。これについてさらに詳しく調べてみると、2005年(平成17年)9月の発着回数最小週は9月5日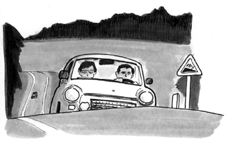 から11日の週で合計飛行回数98回、1日平均14便でした。最大週は19日から25日の週で合計110回、1日平均15.7便にもなっています。しかも、これら22時台の発着航空機の大半は貨物便です。 から11日の週で合計飛行回数98回、1日平均14便でした。最大週は19日から25日の週で合計110回、1日平均15.7便にもなっています。しかも、これら22時台の発着航空機の大半は貨物便です。
このような状況に対して、国は改善に努めてきましたが、昨年度はさらに増加したということです。このため国は、今年3月、乗り入れ航空運送事業者に「成田空港と地域の共生の重大性に鑑み、厳重に対応するよう万全を期されたい。発着予定時刻と実運航時刻に著しい乖離が恒常的にある場合は、公表等の措置を講ずる。21時台出発予定の貨物便への集荷・配送の効率化に努め、21時45分以降に運航する便は、スケジュールをできるだけ繰り上げること」とした指導文書を出しました。
共生委員は「改善するどころか、年々悪化している」「約束を蔑ろにして、そのままどんどん増えて、気がついた時には増便をお願いしますでは、困る」「確実に実効性の上がる手段をとらなければ、共生そのものが揺らいでしまう」「21時30分以降に出発予定の便が相当22時台に食い込んでいる。ずれ込みを許さないという態度を示すべき」などと指摘しました。
これに対して国は、「憂慮しなければならない事態と思っている。次の対策として、IATAの世界中の航空会社が集まるダイヤ調整会議で、ダイヤ担当の方に直接この主旨を主張する。また航空運送事業者へのヒヤリングで直接原因究明を行っている」と述べました。
4000m滑走路 22時台発着回数(1日あたり)
| 年度 |
H7 |
H8 |
H9 |
H10 |
H11 |
H12 |
H13 |
H14 |
H15 |
H16 |
H17 |
| 回数 |
9.2 |
9.7 |
10.8 |
11.2 |
11.1 |
10.5 |
11.2 |
12.6 |
11.7 |
12.0 |
14.1 |
※平成17年度分は速報値
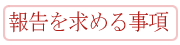
再発防止―とくに北側からの着陸時の対策[落下物]
国・空港会社は、毎冬、航空機氷塊付着状況調査を行っており、今年も1月16日から2週間、目視で確認したと報告しました。それによると、調査機数2,082機のう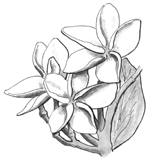 ち着氷機は15機で、昨年の2機に比べて増えていました。主な原因は、機体から水を放出する胴体ドレーンバルブからの流出です。今年は稀に見る厳冬だったため、その影響も考えられるということでした。 ち着氷機は15機で、昨年の2機に比べて増えていました。主な原因は、機体から水を放出する胴体ドレーンバルブからの流出です。今年は稀に見る厳冬だったため、その影響も考えられるということでした。
落下物については、2005年度(平成17年度)は2件の報告がありました。1件は成田市、もう1件は茨城県稲敷市で、いずれも部品でした。
共生委員会は、落下物をなくすためにさらなる努力をするよう要請しました。 |